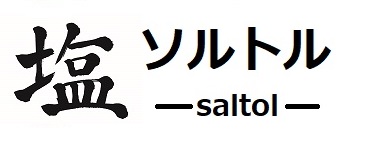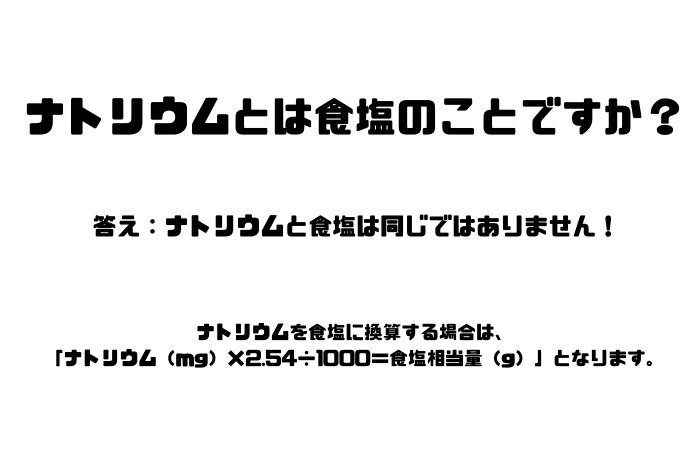食塩相当量とナトリウムの違いを知りたい人向けです。
食品に記載される成分は、食品表示基準によって決まっており、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量及びカロリーは、必ず表示しなければなりません。
特に、ナトリウムについては食塩相当量で表示することとされています。
ただ、過去に製造された食品によってはナトリウム量で記載されている場合があり、その場合は「ナトリウム(mg)×2.54÷1,000=食塩相当量(g)」の計算式で求めることができます。
計算が面倒!という方には、 ナトリウム量と食塩相当量の関係 をご覧ください。
このコラムでは「食塩相当量とナトリウムの違い」や「ナトリウム量から食塩相当量の換算式」などをお伝えしています。
食塩相当量とナトリウムの違い
塩は2つの成分「ナトリウム」と「クローム」で出来ています。つまり、食塩量はナトリウム量ではなく、実際には食塩の約40%がナトリウム量に相当します。
そのため、成分表示は「食塩相当量」や「ナトリウム量」で記載されています。最近は、ナトリウム量○○mg(食塩相当量○○g)と併記されているものもみかけますね。
ただ、現在は食塩相当量で記載することが義務付けられているので、過去に製造された食品のなかにはナトリウム量で記載されているものがります。
食塩相当量の表示はいつから?
現在の食品表示についての基準の適用は、施行日(平成27年4月1日)からとなっています。詳細は、事業者向けのガイドライン|消費者庁で確認することができます。
このガイドラインのなかでは、表示切替のための準備期間として経過措置期間があり、令和2年3月31日までとなっています。
過去に製造された食品ではナトリウム量で記載されている場合があります。その場合は、次に紹介する計算式から食塩相当量を計算しなければいけません。
ナトリウム量から食塩相当量の換算式
実は、ナトリウム量から食塩相当量を計算することができます。
換算式は
食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000
です。
例えば、ナトリウム量が1,400mgと記載されていれば、0.00254をかけると塩分相当量が約3.6gになりますね。
面倒?確かに手間がかかりますよね。
そのような場合には、カゴメ公式サイトでナトリウム量(mg)から塩分相当量(g)を自動計算することができます。スマホにサイトをブックマークしておくと便利です。
ナトリウム量と食塩相当量の関係
いちいち計算するのが面倒だよ、と思われる人は下記の換算表を覚えておくとよいでしょう。
| ナトリウム量(mg) | 塩分相当量(g) |
| 100 | 0.25 |
| 200 | 0.50 |
| 300 | 0.76 |
| 500 | 1.27 |
| 800 | 2.03 |
| 1000 | 2.54 |
| 1500 | 3.81 |
| 2000 | 5.08 |
ただ、すべてを覚えるのは大変なので、ナトリウム量(500mg)が食塩相当量(1.2g)を覚えておきましょう。
単純に250mgで0.6、1000mgで2.4と分かりやすくなります。1日の塩分量を測定しないといけない人以外は便利です。
まとめ
今回のコラムでは「【食塩相当量とナトリウム】何が違う?2つの違いと塩分計算の方法」をご紹介しました。
実は、食塩量がナトリウムではなく、食塩の約40%がナトリウム量に相当します。そのため、ナトリウム量から 食塩に換算するには式によって求めることができます。
ただ、現在は食塩相当量の表示が義務化されているので、このような計算が必要な食品は少なくなってくるでしょう。